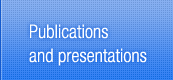研究・教育活動
著書(単著)
Sasaki, M. (1996). Second language proficiency, foreign language aptitude, and intelligence: Quantitative and qualitative analyses. New York: Peter Lang.
要旨:本書は、日本人大学生の第二言語(英語)能力と外国語適性能力、認識能力の関係を、量的・質的に分析したものである。量的分析では、Structural equation modelingを使って、様々なモデルを比較・検討した。その結果、第二言語能力すべてを統括する一般第二言語能力(general factor of second language proficiency)が存在し、それは、一般認識能力と比較的高い相関を持ちながらも同一のものではない、という仮説が支持された。質的分析では、量的分析に使用した標本集団からランダムに抽出した被験者のテスト問題解決過程をプロトコールデータとして採取し、分析した。その結果、第二言語能力の違いは、問題解決過程における査定(assessment)、計画(planning),実行(execution)の各心理段階に現れることがわかった。これは問題解決能力(strategic competence)が、一般第二言語能力に大きく関わっていることを示唆している点で重要である。
著書(共著)
Sasaki, M. & Hu, Y. (2024). Introspective methods. In A. J. Kunnan (Ed), The concise companion to language assessment (pp. 453–472). Wiley-Blackwell.
佐々木みゆき(2022). 「留学による英語学習」中田達也・鈴木祐一(編著) 『英語学習の科学』 (pp.203 - 218).東京:研究社.
Iwashita, N., Sasaki, M., & Stell, A., & Yucel, M. (2021). Japanese stakeholders’ perceptions of IELTS writing and speaking tests and their impact on communication and achievement. IELTS Research Reports Online Series.
Sasaki, M. (2020). Living on the periphery: Cause of despair or source of hope? In L Plonsky (Ed),Professional development in applied linguistics: A Guide for graduate students and early career faculty(pp. 60–62). Amsterdam: John Benjamins.
Sasaki, M. (2018a). Asian perspectives on second language writing pedagogy. In J. I. Liontas (Ed.). The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. NJ: John Wiley & Sons.
Sasaki, M. (2018b). Effects of study-abroad experiences on L2 writing: Insights from published research. In X You (Ed), Transnational writing education: Theory, history, and practice (pp. 138-155). New York: Routledge.
Sasaki, M. (2016a). L2 writers in study-abroad contexts, Chapter 8. In R. Manchón, and P. K. Matsuda (Eds.), The Handbook of Second and Foreign Language Writing. (pp. 161-180). Berline: De Gruyter Mouton.
Sasaki, M. (2016b). English writing instruction in senior high schools: A historical ecological approach. Chapter 5 in T. Silva, J. Wang, J. Paiz, & C. Zhang (Eds). L2 writing in the global context: Represented, underrepresented, and unrepresented voices (pp. 84-109).Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Sasaki, M. (2013a). Introspective methods. In A. J. Kunnan (Ed.), The Companion to Language Assessment, Vol. 3: Evaluation, methodology, and interdisciplinary themes (pp. 1340-1357). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
佐々木 みゆき(2012). 「英語教育」. 日本比較教育学会(編)『比較教育学事典』pp. 51-52. 東京:東信堂.
要旨:本項目は、『比較教育学事典』の中の1項目として、我が国の英語教育の歴史について簡潔に論じたものである。具体的には、我が国の正式な英語教育が始まった1808年から現在までの200年を、エリートに独占されていた1945年までの第一期、義務教育を通して大衆化した1970年までの第二期、実用英語が重視され始めた1990年までの第三期、教育変革の波にさらされた現在までの第四期に分け、それぞれの特徴と影響を与えた主な要因を論じている。さらに、2011年度開始の新学習指導要領の影響などを考慮しながら、次の日本の英語教育「第五期」への展望を最後のまとめとしている。
Sasaki, M. (2009). Changes in EFL students’ writing over 3.5 years: A socio-cognitive account. In R. M. Manchon (Ed.). Writing in foreign language contexts: Learning, teaching, and researching writing in foreign language contexts (pp. 49-76). Clevedon, England: Multilingual Matters.
要旨: 本研究では、22人の日本人大学生が3年半の間にどのように英語作文力と英語で書くことへの動機づけを変化させていったかを、留学期間の効果に焦点をあてて調査した。この本全体の趣旨に沿って、まず、本研究者が過去に行った5つの研究が、方法論と理論的背景の2つの点で、どのように本研究につながったかを時系列順に詳説し、次に本研究の方法や結果を述べた。結果の主なものは、以下の通りである。(1)留学を2ヶ月以上した学生は、3年半で有意に英作文力を伸ばした。(2)留学を4ヶ月以上した学生は、2ヶ月しかしなかった学生に比べて有意に英作文力を伸ばし、「もっと良いものを書きたい」という動機づけを持つようになった。(3)留学を8ヶ月以上した学生だけが、内的動機づけを持つ自律的学習者となり、自ら進んで英作文力向上を目指すようになった。
ダウンロード(pdf)
Sasaki, M. (2005). Hypothesis generation and hypothesis testing: Two complementary studies of EFL writing processes. In P. K. Matsuda & T. Silva (Eds.). Second language writing research: Perspectives on the process of knowledge construction (pp. 79-92). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
要旨: 本研究は、Sasaki (2000)とSasaki (2002)という2つの相補的な研究の成り立ちの詳細を述べることにより、第2言語ライティングに関する量的研究がどのように発展し得るかを提示したものである。まず、Sasaki (2000)は、それ以前に本研究者が行ってきた第2言語での英作文を「結果」としてみなす一連の研究を背景に、その「結果」はどのように実現化されるものであるか、その「プロセス」が知りたいという動機から始まったものである。以前に似たような先行研究が無かったため、この研究は、「関連しそうなものは全て調査する」という「探求的exploratory」なものにならざるを得なかった。次のSasaki (2002)では、このSasaki (2000)の結果をもとに得られた仮説を比較的多くの被験者数を確保し、統計的に検証した。検証した仮説は、「第2言語の熟達した書き手は、学習者に比べ、書く前の計画に比較的多くの時間を費やす」「熟達した書き手は、学習者に比べ、書く途中では計画や翻訳のためにそれほど止まらず、書いた表現を洗練しようとする」「2学期間プロセスライティングの指導を受けた学習者は、熟達した書き手のいくつかの特徴を示すようになる」などである。本論文では、このように、論文の背景となる研究者の「思考の筋道」を詳述しているだけでなく、その論文を雑誌や出版社に送り出版されるまでにプロセスも詳述しており、大学院生の読者の参考となる実践的な側面も持っている。
ダウンロード(pdf)
Sasaki, M. (2003). A scholar on the periphery: Standing firm, walking slowly. In C. P. Casanave & S. Vandrick (Eds.). Writing for scholarly publication: Behind the scenes in language education (pp. 211-221). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
要旨: 本書は、「論文の出版」という研究者の生活に上可欠な活動を、若い研究者、中堅の研究者、学術雑誌の編集者、様々な意味でのハンディキャップを負った研究者の4つの立場から検討した学術啓蒙書である。合計17人の言語教育の分野で活躍している執筆者が、「国際雑誌への論文の掲載」という今まであまり語られることの無かったプロセスを、1人称で描写するという異色の編集方針に基づいて書かれている。佐々木が担当した第15章では、日本という、世界の言語教育の分野では「辺境」に属する場所で、家族の1員としての役割を果たしながら国際雑誌へ論文を投稿することの困難さとやりがいを論じている。具体的には、1996年にデータ採取を始めた研究を、1988年の国際学会で発表し、さらに様々な段階と編集者とのやり取りを経て2000年に国際雑誌に掲載されるまでを詳細に描写した。 Chapter 15 (pp. 211-221)、編者:Christine Pearson Casanave & Stephanie Vandrick
ダウンロード(pdf)
Ross, S., Yoshinaga, N., & Sasaki, M. (2002a). Aptitude-exposure interaction effects on Wh-movement violation detection by pre-and-post-critical Japanese bilinguals. In P. Robinson (Ed.), Individual differences and instructed language learning (pp. 267-299). Amsterdam: John Benjamins.
要旨: 本研究は、日本人学習者が第2言語としての英語において、英語の規則であるsubjacency constraintに対する違反を識別できるかどうかを、(1)母語である日本語からの影響、(2)英語学習開始年齢、(3)言語分析能力(外国語適正能力)の個人差の3つの観点から比較・分析したものである。被験者は、過去の英語学習環境が異なる18歳から21歳の129人の日本人大学生である。分析の結果、(1)日本語からのはっきりした影響は見られなかった、(2)調査したthat-trace効果, 関係節、従属節全てからのwh-移動による非文認識において、学習開始時期の影響がみられた(開始時期が早いほど、非分を認識する能力が高い)、(3) that-trace効果に関係するwh-移動においては、言語分析能力が高い学習者は、学習開始時期に関わらず非文認識能力が高いが、母語話者の能力とは大きな違いがあった、(4)従属節からのwh-移動においては、言語分析能力が高い学習者は、学習開始時期に関わらず、母語話者並の非文認識能力があった、の4点がわかった。 編者:Peter Robinson, 11章分担執筆:Steven Ross, Naoko Yoshinaga, Miyuki Sasaki
ダウンロード(pdf)
Sasaki, M. (2002b). Building an empirically-based model of EFL learners’ writing processes. In S. Ransdell & M-L. Barbier (Eds.), New directions for research in L2 writing (pp. 49-80). Amsterdam: Kluwer Academic.
要旨: 本研究は、日本人学習者の英語文章産出のプロセスを、様々な側面から分析したものである。具体的には、12人の「熟練した書き手」と22人の「未熟な書き手」が書いた意見文や書くプロセスのプロトコルデータ(書くのを止めたとき何を考えていたかを、書いた直後に書いているときのビデオテープを見ながら話してもらう)を、「熟練した書き手対未熟な書き手」と「未熟な書き手が2学期間のプロセスライティング指導を受ける前と後」で調査・比較した。その結果、先行研究(Sasaki,2000)で得られた8つの仮説のうち、以下のような仮説が検証された。(1)熟練した書き手は、書き始める前に文章全体の構成を詳細に考えるが、いったん書き始めると、未熟な書き手ほどプランのために書くのを止めない。(2)2学期間のプロセスライティング指導の後、未熟な書き手は、英作文力が上がり、書き始めてから何度も止まってプランしないようになったが、依然として翻訳に時間を費やし、熟練した書き手のように表現を工夫する計画を立てるようにはならなかった。最後に、以上のような結果に基づき、試行的にではあるが、熟練した書き手と未熟な書き手の書くプロセスのモデルをフローチャート式に提案した。
ダウンロード(pdf)
Sasaki, M. (2001). An introspective account of L2 writing acquisition. In D. Belcher & U. Connor (Eds.), Reflections on multiliterate lives (pp. 110-120). Clevedon, England: Multilingual Matters.
要旨: 本書は、第2言語を使って様々な分野で国際的に活躍している18人の研究者が、いかに第2言語で読み書きすることを獲得していったかを内省的記述とインタビューの手法によって記録したものである・本研究者の分担箇所では、本研究者自身の外国語としての英語習得の歴史が・母語である日本語での読み書き能力獲得の歴史とともに詳細に記述されている。このような、アカデミックな世界におけるプロフェッショナルな第2言語使用者の言語獲得の内省的記録は他に類例が無く・第2言語教育への示唆に富むものであると思われる。
ダウンロード(pdf)
論文
Michel, M., Atkinson, D., Ribeiro, A. C., Alexopoulou, T., Cappellini, M., Eskildsen, S. W., Gao, X. (Andy), Hellermann, J., Kayi‐Aydar, H., Lowie, W., Mejía‐Laguna, J. A., Ortega, L., Pekarek Doehler, S., Sasaki, M., Sato, M., Thorne, S. L., & Zheng, Y. (2025). Forging common ground in second language acquisition and teaching: A combined synergy statement. The Modern Language Journal, 109(S1), 90–103.
Zheng, Y., Ortega, L., Pekarek Doehler, S., Sasaki, M., Eskildsen, S. W., & Gao, X. (Andy). (2025). Praxeology, humanism, equity, and mixed methods: Four pillars for advancing second language acquisition and teaching. The Modern Language Journal, 109(S1), 64–89.
Sasaki, M., Mizumoto, A., & Murakami, A. (2024). Developmental trajectories of multicompetent writers: An ecological-historical approach to L1/L2 writing abilities and L2 proficiency. Journal of the European Second Language Association, 8(1), 114-130.
Sasaki, M., Mizumoto, A., & Matsuda, P. K. (2024). Machine translation as a form of feedback on L2 writing. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching.
Sasaki, M. (2023). AI tools as affordances and contradictions for EFL writers: Emic perspectives and L1 use as a resource. Journal of Second Language Writing, 62, 101068.
Higuchi, Y., Nakamuro, M., Roever, C., Sasaki, M., & Yashima, T. (2023) . Impact of studying abroad on language skill development: Regression discontinuity evidence from Japanese university students. Journal of the Japanese and International Economies, 70(101284)1-13.
Roever, C., Higuchi, Y., Sasaki, M., Yashima, T., & Nakamuro, M. (2022). Validating a test of L2 routine formulae to detect pragmatics learning in stay abroad. Applied Pragmatics,
Higuchi, Y., Nakamuro, M., & Sasaki, M. (2021). Impacts of an information and communication technology-assisted program on attitudes and English communication abilities: An experiment in a Japanese high school. Asian Development Review, 37(2), 100-133.
Sasaki, M., Baba, K., Nitta, R., & Matsuda, P. K. (2020). Exploring the effects of web-based communication task on the development and transferability of audience awareness in L2 writers. Australian Review of Applied Linguistics. 43(3), 277-301.
Sasaki, M. (2018b). Application of diffusion of innovation theory to educational accoutability: the case of EFL education in Japan. Language Testing in Asia, 8 (1).
Sasaki, M., Mizumoto, A., & Murakami, A. (2018). Developmental trajectories in L2 writing strategy use: A self-regulation perspective. TheModern Language Journal, 102(2), 1-18.
Higuchi, Y., Sasaki, M., & Nakamuro, M. (2017). Impacts of an ICT-assisted program on attitudes and English communicative abilities: An experiment in a Japanese high school. RIETI Discussion Paper Series 17-E-030
Sasaki, M., Kozaki, Y., Ross, S. J. (2017). The impact of normative environments on learner motivation and L2 reading ability growth.The Modern Language Journal, 101(1), pp. 163-178.
佐々木 みゆき(2014). 「留学が第二言語ライティングに与える影響についての研究:回顧と展望」. 『第二言語としての日本語の習得研究』17, pp. 97-111.
梗概: 本稿では,留学が第二言語ライティング発達に与える影響について,(1)最新の理論的枠組みから見た研究の歴史,(2)現時点での研究成果,(3)これからの展望の3つの観点から論じる。本稿は,De Gruyter Mouton社から発刊予定のThe Handbook of Applied Linguisticsシリーズの一冊であるThe Handbook of Second and Foreign Language Writing (Rosa M. Manchón,Paul Kei Matsuda編) の第8章:L2 writers in study-abroad contextsの概要を,同社の許可を得て,言語習得を学び始めた初心者にもわかりやすいように,日本語に翻訳したものである。又,「留学の影響」に関する研究自体を初めて学ぶ読者のために,ライティング以外の能力への留学の影響について書かれた部分を多めに翻訳した。
Sasaki, M. (2013a). Introspective methods. In A. J. Kunnan (Ed.), The Companion to Language Assessment,Vol. 3: Evaluation, methodology, and interdisciplinary themes (pp. 1-18). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
佐々木 みゆき(2013b). 「第2言語ライティング行動発達の研究方法を求めて:歴史生態学的方法の可能性」『第24回第二言語習得研究会(JASLA)全国大会予稿集』pp.112-117. 第二言語習得研究会.
要旨: 本論文では、過去20年間に本研究者が行ってきた「日本人学習者の英語ライティング行動の研究」を理論と方法の両面から振り返り、将来有望な方法論を展望する。具体的には、研究の対象と分析方法の変遷を例に取りながら、研究者にとって永遠のテーマである「何をどのように分析すれば妥当性のある結果が出るのか」について考察する。さらに、本研究者の最近の論文投稿経験を詳述することにより、「論文を望む雑誌に掲載してもらう」プロセスの厳しさと意義についても述べたい。
Sasaki, M. (2012a). The Modern Language Aptitude Test (Paper-and-Pencil Version). Language Testing, 29, pp. 315-321.
要旨: 本評論は、1959年以来現在まで50年以上にわたって世界中で使われ続けて来た外国語適性テストであるThe Modern Language Aptitude Test(the MLAT)を、過去50年の第2言語習得論との移り変わりとの関係を中心に、過去、現在、未来の観点から論じることを目的としている。アメリカ合衆国兵士の外国語教育の効率化のために開発されたthe MLATは、長期で詳細な実験結果を元に作成され、作成者のJ.B.Carrol博士とS.M.Sapon博士の先見性もあり、現在まで多くの国の公的機関や研究目的のために使用されている。しかし、過去50年で第二言語能力観が大きく変容しため、将来妥当性のある使い方をするためには、他のテストとの併用や、多面的能力の一部を予測するものとして使用される事が望ましい。
Sasaki, M. (2012b). Changing relationships among L2 writing strategies, L2 proficiency, and L2 writing ability: A dynamic systems approach. The JACET International Convention Proceedings: The JACET 51st International Convention (pp. 145-146).
要旨: 本研究は、37名の日本人大学生の英語ライティング力とライティング方略の変化を3年半にわたって観察した長期的研究である。具体的には、研究当初の参与者の「英語ライティング学習への動機づけ」がその後の英語ライティング力やGlobal Planning, Local Planning, L1-to-L2 Translationという3つの方略の発達にどのような影響を与えたかを、現在応用言語学で最も注目されているDynamic Systems Theoryアプローチを使って調査した。その結果、以下のようことがわかった。(1)研究当初の動機づけの違いは、その後のライティング方略の発達に統計的にも有意な影響を与えた;(2)参与者のライティング方略の発達は、認識能力と環境要因の変化の両方から影響を受けた;(3)Dynamic Systems Theoryアプローチの使用は、参与者の変化を個人レベルとグループレベルの両方で捉えるのに有益であった。
Sasaki, M. (2012c). An alternative approach to replication studies in second language writing: An ecological perspective. Journal of Second Language Writing 21(3), pp. 303-305.
Sasaki, M. (2011). Effects of varying lengths of study-abroad experiences on Japanese EFL students’ L2 writing ability and motivation: A longitudinal study. TESOL Quarterly, 45, pp. 81 – 105.
要旨: 本研究は、37人の日本人大学生の3年半にわたる英語ライティング力と英語ライティングへの学習意欲の変化を追跡調査し、社会文化的視点の一つである活動理論の枠組みを使って分析したものである。その結果、以下のようなことがわかった。(1)学習者の第二言語ライティング力は直線的には変化しない。(2)2ヶ月以上留学した学生は英語ライティング力が伸びたが、国内に留まった学生は伸びなかった。(3)留学した学生は、英語を使う自分が想像できる「想像上のコミュニティ」を形成し、動機付けを高めた。(4)4ヶ月以上留学した学生は、それ以外の学生より有意に英語を書く力を伸ばした。(5)8ヶ月以上留学した学生のみが英語ライティングを自主的に学習する自律的学習者となった。
Download PDF
Sasaki, M. (2008). The 150-year history of English language assessment in Japanese education. Language Testing, 25, pp. 63-83.
要旨: 本研究は、150年にわたる日本の学校英語テストの歴史を、公的学習目標を基準に(1)英語教育がエリートに独占されていた1860年~1945年、(2)英語が初めて義務教育の一部となった1945年~1970年、(3)高まる国際化の中で英語が外国人とのコミュニケーションの手段と考えられ始めた1970年~1990年、(4)教室に様々な革新的変化が導入された1990年以降、の4つの時代に分けて論じている。以上4つの時代を通じて、日本の英語テストは、政治、経済、人口変動や学術理論の変化などから様々な影響を受けながら発展してきたことがわかる。
Sasaki, M. (2007). Effects of study-abroad experiences on EFL writers: A multiple-data analysis. Modern Language Journal, 91, pp. 602-620.
要旨: 本研究は、4~9ヶ月の英語圏への留学が、日本人英語学習者の英語力と英語ライティング力にどのような効果をもたらすかを調査したものである。具体的には、留学を経験した7人の英語専攻の大学生と日本に残った6人の大学生を、留学を含む1年間の前後で比較した。結果として、留学をしなくても一般的な英語力は上がるが、留学は英作文力と英作文を書く流暢さに効果があった。また、留学をした学生のみが、より良い英作文を書きたいという意欲を持つようになった。
Sasaki, M. (2004). A multiple-data analysis of the 3.5-year development of EFL student writers. Language Learning, 54, pp. 525-582.
要旨: 本論文は、11人の日本人学習者の英語ライティング行動にまつわる変化を、書いたテキスト、書く時間、ビデオ録画画面を見ながら本人がどんな思考過程をたどったかを説明するプロトコールデータなどを使い、3年半にわたって調査したものである。被験者本人が自分の変化の原因についてどう思うかを語ったインタビューデータが、上記の量的データを補足している。さらに、3年半の観察期間の間に、6人の被験者が2~8ヶ月英語圏に留学したため、本研究はまた、留学の効果を記録・分析する結果ともなった。本研究の結果は、次の3点にまとめられる。(1)11人の被験者は、3年半で統計的に有意に、英語力、英作文力及び書ける量(流暢さ)を向上させた。また、英作文に対する自信を向上させた。(2)留学は、効果的なライティング方略の学習やより良い作文を書こうとする動機づけに有効だった。(3)被験者の誰も、Sasaki(2002)で研究対象となった、外国語としての英語ライティングの専門家のような能力は獲得しなかった。
Hirose, K., & Sasaki, M. (2000a). Effects of teaching metaknowledge and journal writing on Japanese university students’ EFL writing. JALT Journal, 22, pp. 94-113.
要旨: 本研究では、横断的研究で抽出された英語説明文に関するメタ知識と規則的に英文を書く経験の2要因が日本人学習者の英作文力に及ぼす効果を縦断的に調査し。12週間にわたり上記2要因を2グループで教授した結果、両グループとも明示的なメタ知識は増えたが、作文力の点で有意に向上したのは、英文も定期的に書いたグルーブのmechanicsの点のみであった。これらの結果を基に、今後の作文研究に与える示唆・課題を検討した。
ダウンロード(pdf)
Sasaki, M. (2000b). Effects of cultural schemata on students’ test-taking processes for cloze tests: A multiple data source approach. Language Testing, 17, pp. 85-114.
要旨: 本研究はクローズテストに使われる語のいくつかを解答者に身近な語に置き換えることによってどのような影響が現れるかを、得点、解答に使われた情報量、テスト終了後の内容理解の量と質等の面から調査したものである。その結果、文化的に身近な語を含むテストを受けた被験者は、そうでない被験者に比べて、テスト得点が高いばかりでなく、内容をより深く理解し、また、問題を解こうとする動機づけも高いことがわかった。
Sasaki, M. (2000c). Toward an empirical model of EFL writing processes: An exploratory study. Journal of Second Language Writing, 9, pp. 259-291.
要旨: 本研究は、第2言語学習者の文章産出のプロセスを、様々な側面から分析したものである。具体的には、「熟練した書き手」や「未熟な書き手」が意見文を書くプロセスのプロトコルデータ(書くのを止めたとき何を考えていたかを、書いた直後に書いているときのビデオテープを見ながら話してもらう)を詳細に調査・比較した。その結果、以下のようなことがわかった。(1)熟練した書き手は、書き始める前に文章全体の構成を詳細に考えるが、いったん書き始めると、未熟な書き手ほど書くのを止めない。(2)熟練した書き手と未熟な書き手が使う方略の違いには、第2言語能力の違いが関係しているようだ。(3)3か月間のプロセスライティング指導の後、未熟な書き手は、いくつかの熟練した書き手の方略を学んだが、依然として翻訳に時間を費やし、熟練した書き手のように詳細で構造的な計画を立てるようにはならなかった。次の研究では、被験者数を増やし、この結果を検証する必要がある。
Sasaki, M., & Hirose, K. (1999). Development of an analytic rating scale for Japanese L1 writing. Language Testing, 16, pp. 457-478.
要旨: 本研究は、日本人大学生を対象とした国語作文評価基準を4段階に分けて開発したものである。第1・2段階で代表的な評価項目を含むアンケートを作成・実施し、第3段階で、得られた6つの評価の柱の重み付けの可能性を検討した。第4段階での試行実験の結果、得られた評価基準は、従来使用されてきた基準に比べて信頼性・妥当性が高いことがわかった。
Sasaki, M. (1998). Investigating EFL students’ production of speech acts: A comparison of production questionnaires and role plays. Journal of Pragmatics, 30, pp. 457-484.
要旨: 本研究は、語用論能力測定法である筆記アンケートとロールプレイ法を、応答内容や母語話者の評価等の点から比較した。日本人英語学習者の依頼と拒否(4場面)の表現を分析した結果、2方法への応答には違いが見られ、実施の容易なアンケート法の結果は、必ずしも実際の言語使用能力を反映するとは言えないことがわかった。
Sasaki, M. (1997). Topic continuity in Japanese-English interlanguage. International Review of Applied Linguistics. vol. 35, pp. 1-21.
要旨: 本研究は、ある日本人学習者の日英語の中間言語において、話題(topic)がどのように導入され、維持され、変化していくかを分析したものである。分析の結果、中間言語のtopic-making systemは、第一言語、第二言語の両方と共通点を持ちながらも、言語普遍性に沿った独自の組織性を持っていることがわかった。
ダウンロード(pdf)
Sasaki, M., & Hirose, K. (1996). Exploratory variables for EFL students' expository writing. Language Learning, 46, pp. 137-174.
要旨: 本研究では、試行実験で得られた日本人大学生の英作文能力の説明要因を、多人数(70人)の被験者を使って検証した。統計処理による量的分析の結果、英語力、国語作文力、英語説明文に関するメタ知識の3要因で、英作文力の54.5%を説明することがわかった。また、質的分析の結果、good writersの特徴として、効果的なstrategiesを使用していること、日英双方にfluencyがあること、書くことに自信を持っていること、高校時代に英語を書いた経験が豊富であること等がわかった。
佐々木 みゆき(1995)
Reliability of an ESL Placement test: Comparison of Classical true score theory and generalizability theory
渓水社「英語教育学研究:松村幹男先生退官記念論文集」pp. 410-420
要旨: 本研究では、Classical True Score Theory(CTS Theory)と、Generalizability Theory(G-Theory)の二つの理論を使って、第二言語としての英語のプレースメントテストの信頼性を比較・検討した。その結果、G-Theoryは、CTS Theoryでは上可能だった具体的なエラー要因の解明や、次のテスト実施の際の問題数や合格基準点再設定のための情報提供に優れていることがわかった。
Hirose, K., & Sasaki, M. (1994). Explanatory variables for Japanese students' expository writing in English: An exploratory study. Journal of Second Language Writing, vol. 3, pp. 203-229.
要旨: 本研究では、日本人大学生の英作文能力の説明要因を抽出した。統計処理による量的分析の結果、英語力と国語作文力が、英作文力の74.5%を説明することが分かった。又、質的分析の結果good Writersの特徴として、効果的なstrategiesを使用している、書くことに自信を持っていること、教室外での書いた経験が豊富であること等がわかった。
Sasaki, M. (1993a). Relationships among second language proficiency, foreign language aptitude, and intelligence: A structural equation modeling approach. Language Learning, 43, pp. 313-344.
要旨: すべての第二言語運用能力に影響を与える「一般第二言語能力(G-SLP)」は、多くの先行研究でその存在が認められながらも、内容が解明されていない。本研究は、そのG-SLPと、外国語適性、言語知能、類推力などを支配している「一般認識能力」との関係を構造方程式モデルを使って調査したものである。調査の結果G-SLPは、一般認識能力と比較的強い関係(r=0.65)を持ちながらも、全く同一のものではないことがわかった。
Sasaki, M. (1993b). Relationships among second language proficiency, foreign language aptitude, and intelligence: A protocol analysis. Language Learning, 43, pp. 469-505.
要旨: 本研究は、「一般英語能力」と「一般認識能力」の関係を構造方程式モデルで量的に調査した研究の、質的補完をするものである、方法論的には、被験者がテスト問題を解く際のプロトコール・データを使って、構造方程式分析に表れた得点因子間の関係を分析した。分析の結果、英語能力と認識能力を結びつけているものの一つとして、問題解決能力があることが明らかになった。
Sasaki, M. (1991a). A comparison of two methods for detecting differential item functioning in an ESL placement test. Language Testing, 8, pp. 95-111.
要旨: 本論文は、小グルーブ(N≦100)を対象としたDIF(同能力の二つのグルーブに対して異なった動きを示すテスト項目)検出の2方法(Rasch Model MethodとScheuneman's chi二乗)を比較したものである。2方法の検出した項目は重複が少ないため、二つの方法は対立的としてではなく、補完的に用いられるべきだと提案している。
Sasaki, M. (1991b). An analysis of sentences with nonreferential there in spoken American English. Word: Journal of the International Linguistic Association, vol 42, pp.157-178.
要旨: 本研究では米語口語における「there be構文」の用法が、文脈により、意味的、統語的に変化することを実証した.文レベルでの分析では差は現れないが、談話レベルでの分析の結果、論理主語は新情報を導入して、その話題は後の文脈に引き継がれること、また論理主語はその談話の中のより広い話題と関連がある場合もある等、従来からの論理主語が新情報を担う」という考え方とは異なる場合もあり得ることを指摘した。
ダウンロード(pdf)
山田 純・佐々木 みゆき(1990a)
言語と知覚と思考 --その虚と実
英潮社新社「ことばと文学と文化と:安藤貞雄博士退官記念論文集」pp. 445-457.
要旨: 本研究では、まず、「言語が知覚を支配する」とする言語相対説に対する反論を、いくつかの実例を示して論じた。一方、それが適応され得るかもしれない事例として、日英語間で、加算名詞、上加算名詞の区別の存在が知覚に与える影響を日米の児童を対象に調査した。その結果、小学2年時においては、名詞を分類する際、アメリカ人児童のほうが、加算、上加算の影響を強く受けているように見えるが、物質認識力の影響が強まると思われる小学5年生では、日米の差は縮まることがわかった。この結果は、言語の知覚への効果について、今後の研究に可能性を示唆している。
Sasaki, M. (1990b). Topic prominence in Japanese EFL students' existential constructions. Language Learning, 40, pp. 337-368.
要旨: 本研究は、日本人英語学習者を対象に英語の「There be構文」習得に関して、学習者の言語能力によるtopic-prominenceの度合の変化を調査した。その結果、言語能力が高くなるにつれて、topic-comment構造からsubject-predicate構造へ中間言語が変化すること、また、言語能力が低いと、subject-predicate構造を学習者が知っていても、自発的にはそれを用いない傾向があることを実証した。
ダウンロード(pdf)
Yamada, J., Sasaki, M., & Motooka, N (1988). Copying, reading, and writing of Kana and simple forms by Japanese preschoolers. Perceptual and Motor Skills, vol. 66, pp. 387-394.
要旨: 本研究は、42人の日本人幼稚園児を対象に、ひらがな及び図形の筆写能力と読解・音読能力の関係を調査した多重回帰分析の結果、ひらがな筆写の速度と一度に筆写できる量は、被験者の読み、書く力の差を有意に説明することがわかった。このことから、ひらがな筆写は、就学前の日本人児童の読み書き能力を測定する信頼性の高い尺度に成り得ると主張している。
佐々木 みゆき(1987a)
Linguistic Change in interlanguage: Formula X
『中国地区英語教育学会研究紀要』第17号 pp. 171-177
要旨: 本研究では、米国で第2言語として英語を習得している日本人女児の自発的発話に頻繁に観察された「名詞句+be動詞+X(最低一つの一般動詞の原形または過去形を含む)」という構造をとりあげ、その形式と機能の変化を記述・分析した。意志伝達のための方略として使われたこの構造は、被験者の英語能力の向上に従って、topic-comment構造からsubject-predicate構造へと推移した。この変化は、被験者の中間言語組織全体の変化を反映しており、中間言語が統一的な規則に支配されていることを示唆している。
佐々木 みゆき(1987b)
Change in interclausal relation: Universal side of second language acquisition
『中国地区英語教育学会研究紀要』第17巻 pp. 43-53
要旨: 本研究では、自然な環境で英語を習得している9歳の日本人女児の10ヶ月にわたる自発的発話の中で、節と節を結ぶ関係が言語形式と言語機能の両面でどのように変化するかを分析した。その結果、本被験者の中間言語における節間の接続には、等位接続と従属接続の両方が観察され、後者には副詞的接続、名詞的接続、形容詞的接続が見られたこと、さらに、英語能力の向上について、topic-comment構造をもつloose conjunctionから、subject-predicate構造をもつtight subordinationの流れに沿った変化が観察されたと報告している。
Sasaki, M.(1987c)
Interlanguage development: A case study of a child
修士論文 広島大学 82ページ
要旨: 本研究では、自然な環境で英語を習得している9歳の日本人女児の10ヶ月にわたる自発的発話をデータとし、その中間言語の言語形式と言語機能の関係及びその変化を記述・分析した.その結果、意志伝達方略の一種として使われた、be動詞にさまざまな要素が付帯する構文や、節と節との関係の変化から、被験者の言語形式が、topic-prominenceからより文法的なsubject-prominenceに移行することを発見した。さらに、この変化は、Givon(1979)が提唱した普遍的言語変化に関するsyntacticization仮説を支持すると主張している。
佐々木 みゆき(1987d)
Is UGUISU an exceptional 'idiosyncratic variation?': Another counterexample to the `natural order'
『中国四国教育学会研究紀要』第32巻 pp. 170-174
要旨: 本研究では、自然な環境で英語を習得する日本人女児の長期的事例研究の結果得られた形態素発達の過程を、日本人の子供を被験者とした同様の研究と比較し、Krashen(1977)で提唱された自然習得仮説に対する反例を提示する。それにより、少なくとも日本語を母語とする子供に関しては、Corder(1967)の唱えるlanguage universalとしての"the built-in syllabus"は、学習者の母語に相当影響を受けることを実証している。
Sasaki, M.(1986)
Second Language Acquisition: A case study
修士論文 米国ジョージタウン大学 58ページ
要旨: 本研究は、米国で第2言語として英語を習得している9歳の日本人女児の中間言語発達の様子を、主に15個の文法形態素習得の観点から、10ヶ月間観察、分析したものである。その結果、形態素習得順序の決定要因として、従来主張されてきた第一言語との相違、簡易化の規則などに加えて、「意味的経済性の規則」(意味上最も重要なものを優先する)を主張した。この法則に従うと、自然な環境での第二言語習得では、意思伝達が可能な段階に達すると言語発達が停止する恐れがあることから、最終到達度を高めるためには適切な指導が肝要であると述べている。
佐々木 みゆき(1985)
幼児の外国語としての英語学習に関する一考察A君の”is it” patternについて
『中国地区英語教育学会研究紀要』第15巻 pp. 75-79
要旨: 本研究は、日本で英語の早期教育を受けている4歳の日本人男児の中間言語の1形態をとりあけ、それが出現する言語環境を分析している。その結果、その形態は英語の正用法、誤用法の両方で用いられ、独自の規則を持つことがわかった。又、機能の面では、この形態が、この被験者のコミュニケーション方略の一つとして重要な役割を担いつつ、言語発達の中間段階として次の言語発達の段階への橋渡しの役割を果たしていると指摘した。
佐々木 みゆき(1984)
初級レベルの外国語としての英語教科書にあらわれる生活語彙について:日本の教科書とドイツの教科書の比較
『中国地区英語教育学会研究紀要』第14巻 pp. 1-4
要旨: 本書は、幼児期・児童期をカバーする早期英語教育向けの3種類の教材にあらわれる語彙を「生活語彙」と定義し、それらの語と、日本と西ドイツの代表的な中学生向け外国語としての英語教科書に出現する語が重なる割合を調べた。調査の結果、日本の教科書は、ドイツのものに比べ、身近な生活語の割合が低く、学習者の興味や動機付けの観点からも、今後の教科書作成や英語授業で考慮すべきであることを指摘している。
研究発表
Sasaki, M., & Suzukida, Y. (2025, March 24). Understanding L2 Texts through Diverse Eyes: A Study of Multilingual English Users' Comprehensibility. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Denver, CO.
Sasaki, M. (2025, March 21).Global perspectives: AI-powered innovations in higher ed second language writing [Invited panel presentation with M. E. Wilson-Patton]. TESOL 2025 International Convention & English Language Expo, Long Beach, CA.
Sasaki, M., Suzukida, Y., Takizawa, K., & Saito, K. (2024, March). What influences L2 readers’ comprehensibility of L2 texts? Interactions between textual characteristics and readers’ profiles. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Houston, Texas.
Sasaki, M., Dwight Atkinson, Lourdes Ortega, Anamaria Sagre, Wander Lowie, Steven Thorne, Simona Pekarek-Doehler & Soren Eskildsen, Marije Michel. (2023, March). Colloquium: Toward commensurability and diversity in complexity: Diverse approaches to second language acquisition/teaching (SLA/T) in dialogue. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Portland, OR.
Sasaki, M. (2021, March). Emergence and transferability of audience awareness in writers of L2 Japanese through web-based exchanges. American Association for Applied Linguistics Annual Virtual Conference.
Sasaki, M. (2021, January). (Invited Speaker). A non-deficit view of multilingual researchers: Transdisciplinary hopes? Inequities in journal publishing: A conversation with multilingual scholars. American Association for Applied Linguistics Webinar Series.
Sasaki, M. (2020, October). (Invited Speaker). Investigating L2 writing development: What lies ahead and beyond. ESRC (Economic and Social Research Council)-JSLARF (Japan Second Language Research Forum) Symposium (Zoom presentation).
Sasaki, M. (2018a, March). (Invited Speaker). Development of L2 writing strategy use: Shared patterns and uniqueness. Public Research Talk at the School of Languages and Linguistics, University of Melbourne, Melbourne.
Sasaki, M. (2018b, March). (Invited Speaker). Development of L2 writing strategy use: A mixed methods approach. Symposium on Academic Writing in an L2 Context. University of Tokyo.
Sasaki, M., & Mizumoto, A. (2017a, March). Longitudinal development in L1 and L2 writing: Shared patterns and individual differences. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Portland, OR.
Sasaki, M. (2017b, March). (Invited Speaker). Effects of study-abroad experiences on L2 writing: Insights from published research. Invited Public Research Talk at the Department of Linguistics, Georgetown University, Washington, D.C.
Sasaki, M. (2017c, May). (Invited Speaker). Development of second language writing ability: Insights from recent research. A special public lecture of Institute for Education and Student Service 2017 co-sponsored by the Japanese section and the English section. Okayama University, Okayama, Japan.
佐々木みゆき (2017d, 6月). (基調講演). 第2言語ライティング研究最前線:長期的研究に見られるパタンと個人差. JACET関西支部春季大会. 甲南大学.
Sasaki, M. (2017e, June). (Invited Speaker). L2 writers in study abroad contexts: Insights from recent studies and pedagogical implications. E-Link Talk, Kansai University, Osaka, Japan.
Sasaki, M. (2017f, July). (Invited Speaker). What causes scoring discrepancies between trained raters? Comparing rating mechanisms in L1 Japanese and L2 English composition assessment. Symposium on Second Language Writing, Chulalongkom University, Bangkok, Thailand.
Sasaki, M. (2017g, September). (Invited Speaker). Measuring L1-L2 writing development with a new longitudinal cluster analysis statistics. Invited Public Research Talk at the Department of Linguistics, Georgetown University, Washington DC.
佐々木みゆき. (2017h,November). (招待講演). 第二言語ライティング研究最前線と教室への応用. 第1回英語指導力向上講座. 愛知県スーパーイングリッシュハブスクール平成29年度外部専門機関と連携した英語指導力向上事業. 千種高校、名古屋.
Sasaki, M., & Mizumoto, A. (2016a, September)(招待パネラー). Developmental trajectories in L2 writing strategy use: Systematicity and individuality. Second Language Research Forum. Teachers College, Columbia University. New York.
Sasaki, M., & Mizumoto, A. (2016b, October). Modeling patterns, uniqueness, and beyond: The development of L2 writing strategy use. Symposium on Second Language Writing, Arizona State University, Tempe, AZ.
Higuchi, Y., Sasaki, M., & Nakamuro, M. (2016c, September). Impacts of online English learning on attitudes and English communicative abilities: Experimental evidence from Japanese high schoolers. 日本経済学会、早稲田大学.
Sasaki, M. (2016d, September). Expanding understandings of interaction: A panel discussion. Initiative for Multilingual Studies (IMS). Georgetown University, Washington, D. C.
Sasaki, M. (2015a, November). Japanese students’ longitudinal development in 2 writing strategy: A historical –ecological approach. Symposium on Second Language Writing, Shandong University, Auckland, New Zealand.
Abstract: This study describes changes in 37 Japanese students’ use of three L2 writing strategies (Global Planning, Local Planning, L1-to-L2 Translation) and asks what factors most critically impacted these changes over a four-year observation period. The students were English college majors with low- to mid-intermediate proficiency and aged 18 when the study began. They were observed at the beginning of their first year and in the middle of their second, third, and fourth years in university. The data also included the students’ scores on standardized L2 proficiency tests, L2 composition scores rated by two independent writing specialists, and in-depth interviews focusing on the participants’ own explanations about any changes in these variables. In analyzing the data, I drew on Gaddis’ (2002) historical-ecological perspective and explored the potential of “retrocasting” as a method for uncovering what critically affected the participants’ use of the targeted L2 writing strategies. Among the cognitive and environmental factors noted over the period, I searched for Gaddis' “points of no return” in the participants’ developmental paths, using as the major tool the participants’ own concurrent and retrospective accounts. I also searched for patterns shared by the participants in addition to individual differences commonly focused upon in a standard ecological approach. Results reveal that over the period: (1) initial differences in the students' motivations significantly influenced subsequent changes in their use of L2 writing strategies, which continuously interacted with cognitive and environmental changes; (2) the historical-ecological perspective was useful in explaining the students’ development at both the individual and the (traditionally observed) group level; and (3) using the participants’ own accounts helped understand the results of the quantitative analyses, revealing that students’ motivation may be a key factor in understanding their developmental trajectories.
Sasaki, M. (2015b, May). (Invited Speaker). Longitudinal development in L1 and L2 writing: An ecological approach. Symposium on L2 Writing, OISE, University of Toronto.
Abstract: This study describes changes in the L1 and L2 writing abilities of 22 Japanese students and asks what factors most critically impacted these changes over a four-year observation period. The students were English majors with low- to mid-intermediate proficiency and aged 18 when the study began. They were observed at the beginning of their first year and in the middle of their second, third, and fourth years in university. Data included the students’ scores on standardized L2 proficiency tests, L1 and L2 compositions rated by two independent writing specialists, and in-depth interviews about their beliefs about L1 and L2 writing and how and why their writing ability changed as it did over the period. The data analysis draws on Gaddis’ (2002) historical-ecological perspective and explores the potential of “retrocasting” as a method for uncovering what critically impacted the participants’ growth as multicompetent writers.
Sasaki, M. (2015c, March). Dynamic changes in the relationship between L1 and L2 writing abilities and L2 proficiency in Japanese multi-competent writers. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Toronto.
Abstract: This study investigates relational changes in the L1 and L2 writing ability and L2 proficiency of 22 Japanese students along with the factors that most critically influenced these changes over a four-year period. The students were British and American Studies majors with low- to mid-intermediate L2 proficiency and aged 18 when the study started. They were observed at the beginning of their first year and in the middle of their second, third, and fourth years in university. Data included the students’ scores on standardized L2 proficiency tests, L1 and L2 compositions, and in-depth interviews about their beliefs about L1 and L2 writing and their experiences regarding their L1 and L2 writing development. In analyzing the data, I drew on Gaddis’ (2002) historical-ecological perspective and explored the potential of “retrocasting” as a method for uncovering what crucially impacted the participants’ growth as writers, who are multi-competent in that they can strategically choose various skills and knowledge types in the L1 and L2 to write the most effective texts for a given situation. Results reveal that over the period: (1) a previous lack of writing instruction caused the participants’ first-year L1 and L2 writing ability to be more tightly correlated because their individual composing expertise, which transcended both L1 and L2, was the only ability they could depend upon; (2) their motivation to learn the L2 tended to lead to improvements in their L2 proficiency and L2 writing ability, which strengthened the correlation between the two but weakened that between L1 and L2 writing ability; and (3) components of the students’ multi-competence included their beliefs about L1 and L2 writing, acquired skills through instruction, and their sociocultural experiences accumulated over time.
Sasaki, M. (2014a, March). Longitudinal development of L1 and L2 writing in Japanese students: An Ecological approach. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Portland, OR.
佐々木 みゆき(2014b, June). (招待講演). 第二言語ライティング能力の長期的発達:実証主義的アプローチと生態学的アプローチの接点. 竹内理氏と柳瀬陽介氏とのシンポジウム.第30回JACET中部支部大会、椙山女学園大学.
梗概: 本発表の背景は、日本人学習者22名の大学4年間の英語力と日英の作文力がどう変化し、それは何に影響を受けるかについての研究である。その研究では、学習者の変化に影響を与える要因を探るため、大学1年から1年に一回収集した英語標準テスト得点や、それぞれの専門家に採点してもらった日英作文の得点等の量的変化に加え、「その変化をもたらした要因についての学習者自身の見解」をデータとして加えた。本発表では、このような、「当事者の来歴や受け止め方」を重要と考え、学習者の変化に環境などの外部要因の影響が不可欠と考える「生態学的アプローチ」と、研究対象に共有化される傾向をつきとめることを究極の目標とする「実証主義的アプローチ」の接点を求めて模索する本研究者自身の困難な経験を語りたい。
佐々木 みゆき(2014c, June). (招待講演). 第2言語ライティング研究:目の前の現象をどう捉えて、未来に生かすか. 第19回関西英語教育学会、関西学院大学.
梗概 本セミナーでは、過去20年間に本研究者が行ってきた「日本人学習者の英語ライティング行動の研究」を理論と方法の両面から振り返り、将来有望な方法論を展望する。まず、過去の研究として、1990年代に行った「日本人の英作文力は、他のどんな能力(例:国語作文力)と関係が深いか」という能力関係論の研究や、2000年代前半に行った、「プロと素人の書き手の書く手順はどう違うか」というプロセスの研究を紹介する。どちらの研究も、量的認知データを扱う実証主義の研究である。2000年代後半には、本研究者にとって転機となった「大学生の英作文行動を4年間観察する長期的研究」を行った。参与者の変化には、「留学」や「就職活動」などの環境要因が深く関わっていたため、認知能力のみに焦点をあてた実証主義的枠組みから、環境の影響も考慮に入れた生態学的アプローチに転換を余儀なくされた。現在も「学習者の長期的変化」は本研究者の最大の関心事であるが、方法論上の課題として、①予測不可能な発達過程において、どのように「最も影響力のある要因」を探し出せるのか、と②個人差とグループの傾向はどのように併存できるのか、の2点を模索中である。本講演では、このような問題を解決し得る方法として、Gaddis (2002)の推奨する歴史生態学的アプローチを応用した現在進行中のプロジェクトの暫定結果を報告する。この報告を通して、異領域の方法論の第二言語習得研究での有用性を示唆したい。
Sasaki, M., Ross, S. J., & Kozaki, Y. (2014d, August). Impacts of group motivational dynamics on Japanese students’ EFL development. International Conference on Motivational Dynamics and Second Language Acquisition. Nottingham University, Nottingham.
要旨: This mixed-methods longitudinal study explores the contextual effect of group norms operating within EFL classes on the year-long development of Japanese university students’ English proficiency. A total of 1,149 students nested in 44 language classes from 12 different departments in 8 universities took three forms of a standardized English test (SLEP, Educational Testing Service): before instruction, after one semester, and at the end of the second semester. During the second semester, the students were surveyed regarding the intensity of their motivation to learn English as a foreign language, two types of career-related aspirations (aspiration to professional pursuits and orientation toward the social mainstream), and their perceptions of the magnitude of their classmates’ career-related aspirations (as listed above). Methodologically, multi-level modeling (Raudenbush & Bryk, 2002) enabled us to examine the relationships between these explanatory variables and the students’ L2 proficiency gains both at the individual and contextual level simultaneously. These quantitative results were supplemented by the students’ accounts explaining in interviews how they felt about their own English development and the overall classroom atmosphere regarding their classmates’ motivation to learn English and their future career aspirations. The quantitative results indicate that for these participants, individual development did not differ when initial L2 proficiency was controlled. However, class-level development significantly differed over the year, a finding explained by one form of normative career aspiration (aspiration to professional pursuits). These results were confirmed by the interview data, suggesting that improvement within each class as a whole can be greatly influenced by its individual members’ perceptions of their classmates’ future career aspirations. These findings suggest the importance of creating motivating classroom norms, which may eventually make a difference at the level of individual growth.
Sasaki, M. (2013a, March). Reexamining writing assessment rubrics in the classroom
Colloquium presented with Paul Kei Matsuda, Lia Plakans, Deborah, Crusan, Jill Jeffery. Annual Convention of Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), Dallas, Texas.要旨: 本コロキアムの目的は、第二言語作文のおける公正で一貫性のある評価のための、評価基準(Writing assessment rubrics)の重要さについて様々な角度から検討することである。具体的には、多様な評価基準を建設的に使うために、教育の現場で、そもそも、基準を使うべきか、使う場合は、基準を使う理由と使用法などを4人の専門家で議論した。
Sasaki, M. (2013b, October). (基調講演). English writing instruction in senior high schools in Japan: Its goals, its product, and its future. Symposium on Second Language Writing, Shandong University, Shandong, China.
Sasaki, M. (2013c, November). (基調講演). Development of Japanese Students as Multicompetent Writers: An Ecological Perspective. International Symposium on EFL Writing in East Asia: Crossing the Boarders. Chiba, Japan.
佐々木 みゆき(2013d, November).(招待講演). 『全入時代の高校3年生の英語ライティング力:どこまで書けるのか、書ければ良いのか』第11回英語教育改革フォーラム. 東京国際大学.
佐々木 みゆき(2013e, December).(基調講演). 「第2言語ライティング行動発達の研究方法を求めて:歴史生態学的方法の可能性」.第24回第二言語習得研究会(JASLA)全国大会. 広島大学.
Sasaki, M. (2012a, February). (Plenary Speaker). Studies of Japanese EFL writers: Past, present, and future. The Fourth Symposium on Writing Centers in Asia. National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Japan.
要旨: 本講演では、本発表者の過去20年に渉る第二言語ライティング研究の歩みを、内容と方法論から概観した。本研究者は、この20年の間に実証主義的な量的研究者から、社会文化的要因の影響を重視するポスト実証主義的な研究者へと変化してきた。現在は、学習者の長期的発達に焦点をあて、認知能力と外的要因の相互的影響の変化を、最も妥当性のある形で分析できる方法論としてのダイナミックシステムアプローチに注目している。本講演の後半は、現在進行中の研究を例にとり、この方法論を第二言語ライティング力発達研究に応用する際の利点と問題点を中心に議論した。
Sasaki, M. (2012b, August). Effects of different learning environments on various types of English skills and knowledge in Japanese students: Mixed-method approaches. Symposium presented with Naoko Taguchi, and Tomoko Yashima at the JACET 51st International Convention, Aichi Prefectural University, Aichi, Japan.
要旨: 本シンポジウムは、様々な学習環境(留学、イマージョン、国際ボランティア)が第二言語能力の発達に与える影響を、日本人英語学習者である大学生を対象に、量的データと質的データの両方を使って明らかにしようとした3つの研究を統合的・有機的に紹介したものである。
Sasaki, M., & Shimokido, T. (2011a, March). Effects of varying lengths of study-abroad experiences on product and process in Japanese students learning to write in English. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Chicago, Illinouis.
要旨: 本研究は、37名の日本人大学生の3つの英語ライティング方略(Global Planning, Local Planning, L1-to-L2 Translation)の3年半にわたる変化が、彼らの一般英語力と英作文力の変化に、どのように影響を与えられつつ変化するかを、社会文化的視点から調査・分析したものである。その結果、以下のようなことがわかった。(1)3年半の間に一般英語力と英作文力は、留学期間を媒介変数にして関係を強化した。(2)学習者の留学期間は、学習者のGlobal Planningに最も大きな影響を与えた。(3)学習者のLocal PlanningとL1-to-L2 Translationの使用への留学期間の影響は、Global Planningほど直線的でなく、他の外的要因(例:アルバイト、就職活動)の影響も受けていた。(4)以上の学習者の変化は、ダイナミックで非直線的で外界への適応によって変化する「複雑系理論」でより適切に説明できることがわかった。
Sasaki, M., Baba, Kyoko, Nitta, R., Matsuda, P. K. (2011b, June). Effects of web-based communication tasks on L2 students’ development of a sense of audience. Symposium on Second Language Writing, Howard International House, Taipei.
Sasaki, M. (2011c, June).(Invited Speaker). Colloquium: Becoming a writing researcher. Presented with Icy Lee, Hui-Tzu Min, Suresh Canagarajah, and Paul Kei Matsuda at the Symposium on Second Language Writing at Howard International Hotel, Taipei.
Sasaki, M. (2011d, October). (Invited Speaker). A dynamic systems approach to interaction among L2 writing strategy use, L2 proficiency, and L2 writing ability as these develop in Japanese students. Paper presented at the Second Language Studies Lecture Series, University of Hawai’i at Manoa.
要旨: 本講演では、本発表者が現在取り組んでいる最新の研究について発表した。この研究では、長期的発達分析のための最新の理論であるダイナミックシステムアプローチ(de Bot & Larsen-Freeman, 2012)を枠組みとして、37人の日本人大学生の3つの英語ライティング方略(Global Planning, Local Planning, L1-to-L2 Translation)使用と、一般的な第二言語能力と第二言語ライティング力の相互作用の変化を分析した。未解決の問題として、本来個人を対象としてきたダイナミックシステムアプローチを集団に適用することの妥当性と問題点も議論した。
Sasaki, M. (2010a, March). Effects of a six-week study-abroad program on L2 writing: A case study of four Japanese learners of English, American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Atlanta.
要旨: 本研究は、6週間の英語圏の留学が日本人大学生の英語ライティング力と英語を書くことへの動機づけに及ぼす影響を調査したケーススタディである。留学当時1年生だった学生2名のその後の3年間の変化と、留学当時2年生だった学生2名のその後の2年間の変化を、エンゲストローム(1989)の拡大活動理論の枠組みを通して調査した。その結果、(1)6週間の留学は英語ライティング力を向上させなかった。(2)その後10ヶ月英語圏へ留学した学生3名は英語ライティング力を向上させた。(3)外国語環境では、英語を書くことの必要性が低いため、学生の動機づけを強化・維持することは困難である。ということがわかった。
Sasaki, M. (2010b, May). Japanese students learning to write in English: A longitudinal analysis of the effects of study-abroad experiences. Symposium on Second Language Writing, University of Murcia, Spain.
要旨: This study investigated the effects of varying lengths of study-abroad experiences on students’ L2 writing development during their 3.5-year university life. The results revealed significant impacts of their study-abroad experiences on their L2 proficiency development, which interacted with changes in their L2 writing ability and strategy use.
Sasaki, M. (2010c, May). What contributions can study of Japanese EFL learners make to the field of L2 writing? Presented for Language Learning Round Table organized by Professor Ilona Leki of the University of Tennessee, “Cross-Pollinations in L2 Writing Research across Continents” held at the Symposium on Second Language Writing at the University of Murcia, May 2010, (Round Table招待パネラー).
要旨: I focused on my studies where Japanese students had difficulty having or keeping high motivation to study EFL writing. Such motivational issues had rarely been investigated in the past ESL writing literature. Comparing EFL and ESL contexts would reveal the importance of sociocultural considerations in L2 writing research.
佐々木 みゆき(2010年d, 12月)(招待講演) 単独. 第二言語ライティング力の発達:認知と環境、ProcessとProduct、Etic的アプローチとEmic的アプローチ
大学英語教育学会中部支部定例研究会
要旨: 本発表では、ほぼ同じ英語力と英作文力を備えていた37人の日本人大学生が、3年半の間にどのように英語ライティング力に関わる技能を変化させていったかを、留学期間の効果に焦点をあてて調査したSasaki(2010)の結果を中心に、現在執筆中の論文の結果の一部交えて説明した。主な結果は以下の通りである。(1)留学を1.5か月以上した学生は、3年半で有意に英語力と英作文力を伸ばした。(2)留学を4か月以上した学生は、1.5~2か月しかしなかった学生に比べて有意に英作文力を伸ばし、「もっと良いものを書きたい」という動機づけを持つようになった。(3)留学期間は、学生が英語を書く際の方略使用の変化にも影響した。(4)留学期間が長いほど、作文全体について計画し、整合性や表現についてよく考えるようになった。(5)以上の結果には、留学後に学生が形成した「英語を書くことが想像できるコミュニティ」と、そのコミュニティに喚起される動機づけが関係していた。
Sasaki, M. (2009a, March). (Invited Speaker). L2 writing in EFL higher education. Presentation for the Writing Interest Section’s Academic Session. TESOL Annual Convention, Denver, Colorado.
要旨: The present study is a follow-up of Sasaki (2004) that heuristically examined the changes in Japanese EFL students’ L2 writing behaviors over 3.5 years. In addition to testing hypotheses formulated on the basis of Sasaki’s (2004) results, the present study examined the participants’ changes in L2 writing motivation, employing Yang, Baba, and Cumming’s (2004) research framework. Reflecting on the limitations of the cognitive-only approaches I employed for the past studies, I adopted a more sociocultural perspective (e.g., Thorne, 2005) for the present analysis. The results revealed that over 3.5 years (1) only those students who were motivated enough to spend some time abroad improved their L2 writing ability, (2) only those students who spent some time abroad formed an L2-related “imagined community” that potentially motivated them to improve L2 writing ability, (3) only those students who spent more than four months abroad became motivated to write better in L2, imagining the classes they took abroad even after they came home, and (4) only those students who spent more than eight months abroad voluntarily practiced L2 writing to improve the content of their writing.
Sasaki, M. (2009b, May). (基調講演). Changes in Japanese students’ English writing ability, strategy-use, and motivation during their 3.5 year university life. The 26th Conference of English Teaching and Learning in the Republic of China. National Tsing Hua University, Taiwan.
要旨: The present study reports on the changes in 37 Japanese students’ English writing ability, strategy-use, and motivation during the students’ 3.5-year university life. It is a follow-up to Sasaki (2004) that heuristically examined the changes in 11 Japanese students’ English writing behaviors over 3.5 years. For the present analysis, however, reflecting on the limitations of the cognitive-only approach I employed for Sasaki (2004), I adopted a more social perspective, assuming that students’ cognitive changes are bound to be affected by their socio-cultural environments.
The results of the present study can be summarized as follows:(1) The students’ SA experiences changed the nature, but not the frequency, of their use of the Local Planning strategy; (2) The different length of the students’ SA experiences had a significant impact on their L2 writing ability changes over their 3.5-year of university life; (3) The different length of their study-abroad (SA) experiences had a significant impact on their use of the Global Planning strategy, and possibly on becoming self-regulated writers; (4) Only those students who went abroad formed L2-related “imagined communities” that potentially motivated them to improve L2 writing ability; (5) Only those students who spent more than four months abroad became motivated to write better in L2, imagining the classes they took abroad even after they came home; (6) Only those students who spent more than eight months abroad became intrinsically motivated, and voluntarily practiced to improve their L2 writing, even though such an actions did not directly benefit their future career.
佐々木 みゆき(2009年c,8月)
「アウトプットとしての第二言語ライティング力と動機づけの縦断的研究」
第35回全国英語教育学会(招待シンポジウム)
要旨: 本研究では、「アウトプット」としては光のあたることの少ない「ライティング」を対象とし、日本人大学生が、3年半の間に第二言語としてのライティング力をどのように発展させるかを調査・観察した成果を報告する。本研究者はこれまで主に学習者の英語ライティング力や方略のような認知的側面を研究してきたが(例:Sasaki, 2004, 2007)、学習者を長期にわたって観察した結果、認知的発達には、「留学」や「就職活動」のような外部からの環境要因が重要な役割を占める事もわかった。そこで、本研究では、それらの外部要因の影響を説明するため、近年応用言語学の世界で重要視されてきた「社会文化的視点」を取り入れ、先行研究で特に影響力の大きかった「留学」とその期間の長短の影響に焦点をあて、学習者の英語ライティング能力の発達要因を動機づけの観点から探った。
佐々木 みゆき(2009年d,9月)
「第2言語ライティング力研究」の過去、現在、未来
日本言語テスト学会 第13回全国研究大会(招待シンポジウム)
要旨: 過去20年のL2 Writing Abilityの研究を概観すると「研究対象としてのWhat, How, Why」の観点から分類できる。本発表では、特に、「What→How→Why」と変遷してきた自分自身の研究の歴史を具体例として、「能力とは何か」、「能力を測るとはどういうことか」といった問題についてもヒントが探せればと思う。
Whatの研究には、学習者が書いたテキストの語や構造を習熟度別で比較したものや、作文の質に影響を与える要因を調査したものがある。どちらも「第2言語作文力」や「評価」に直接関わっている。
Howの研究の対象は、「学習者はどんなふうに作文を書くのか」である。第一言語と第二言語の作文プロセスの比較や、expertsとnovicesの比較などがある。このように作文完成までのプロセスを扱うHowの研究は、完成品のみを評価することの多い評価の研究とはあまり縁がないような気もするが、プロセス自体を評価するportfolio assessmentなどに影響を与えている。また、作文力の低い学習者に、作文力が高い学習者の方略である「事前に全体の枠組みを計画する」などを強制すると作文の質があがるのか、もしあがるなら、それは、その学習者の「作文力」と言えるのか、などの興味深い問題も提起する。
Whyの研究は、「良いものを書きたい、書けるようになりたい」と思わせる要因は何か、に関わっている。長期的に学習者の成長を追うケーススタディで扱われることが多く、学習者の認知的側面だけでなく、学習者を取り巻く社会文化的要因まで考慮に入れたものがほとんどである。この種の研究も評価の分野とは縁がうすいように見えるが、同じ作文の課題に取り組んでいても、学習者が、「ただ課題をこなしている」と思っているか、「かつて自分が書いたもののように、より良い作品を生み出したい」と思っているかで、作文の質は変わってくるのではないだろうか。その「質の違い」は「実力の違い」と言えるのか?などの問題は、評価論でも論議の対象になり得ると思う。
Matsuda, P. K., Sasaki, M., Matsuda, A. (2008a, March). Writing in dual voices: A case study of an expert bilingual academic writer. American Association for Applied Linguistics Annual Conference, Washington, D.C.
要旨: 本発表は、日英両方の言語で活躍している日本人研究者が、日英語の2つのアカデミックコミュニティの中でどのように言語を使い分けながら自己構築をしているかを探ることを目的としている。方法論としては、インタビューデータ、業績文書と実際の論文という多元的データを使い、現象学的分析を行った。その結果、対象となった研究者の論文を書く際の言語の選択には、研究の種類(理論的か実験的か)、読者に訴えたいものは何か、職場や学会での役割など多様な要因が関わることがわかった。この結果は、多言語使用者は、言語的要因だけではなく、アイデンティティに関わる能動的動機に基づいて言語選択をするという事実を示している。
Sasaki, M. (2008b, August). Japanese students learning to write in English for 3.5 years: Confirmatory and exploratory approaches. Paper presented in the Symposium titled L2 writing in transnational perspective: Learning-to-write and writing-to-learn dimensions organized by R. M. Manchon, and presented with A. Cumming, A. S. Canagarajah, R. M. Manchon, J. Roca, & L. Murphy with L. Ortega as discussant. AILA 2008: World Congress of Applied Linguistics, University of Essen, Germany.
要旨: 本発表は、”L2 writing in transnational perspective: Learning-to-write and writing-to-learn dimensions”と題された3時間のシンポジウムの1部として、カナダ人、スリランカ人、スペイン人の発表者とスペイン人のdiscussantと共に発表されたものである。本研究者の担当部分は、上記テーマで示されるように、37名の日本人大学生の3年半の英語ライティング力と動機付けの変化を、社会認識論的アプローチから分析することを目的とした研究であった。分析の結果は以下の4つのまとめられる。(1)2ヶ月以上の留学は英語ライティング力に有意の向上をもたらした。(2)英語圏への留学は、学習者の動機付けにつながる「想像上の英語使用コミュニティ」の出現をもたらした。(3)4ヶ月以上留学した学習者のみが「英語をもっと良く書けるようになりたい」という動機付けを持った。(4)8ヵ月以上留学した学習者のみが、英語ライティング力向上への内発的動機付けを持つに至った。
Sasaki, M. (2007a, April). Changes in EFL students’ writing over 3.5 years: Influences of study-abroad experiences and other socio-cognitive factors. Conference on Social and Cognitive Aspects of Second Language Learning and Teaching, The University of Auckland, New Zealand.
要旨: 本発表は、日本人大学生の英語ライティング力と動機付けが3年半の間にどのように変化するかを多面的データを使って観察・調査した研究の一部である。具体的には、22人の大学生を、在学中に英語圏へ留学したグループと留学しなかったグループに分け、英語作文得点、英語を書く際の翻訳方略、英語を書く事への動機付けの3つの観点から分析した。分析の結果、(1)留学したグループのみが3年半で英語ライティング力を伸ばした、(2)4ヶ月以上留学した学生のみが、「より良く書くこと」への意欲を持つようになった、(3)留学は、英語ライティング学習への動機付けに貢献した、などがわかった。
Sasaki, M. (2007b, September). Changes in L2 writing ability and motivation over 3.5 years: A socio-cognitive account. Symposium on Second Language Writing, GAKUIN CITY UNIVERSITY, Japan.
要旨: 本発表は、本研究者の過去15年の研究成果を踏まえ、日本人大学生の英語ライティング力と動機付けが3年半の間にどのように変化するかを、社会認知的観点から分析したものである。具体的には、22人の大学生を、留学経験の有無と留学期間の長さで4グループに分け、英語ライティング力と動機付けの変化とそれらの相互関係を調査した。分析の結果、(1)留学したグループのみが英語ライティング力を伸ばした、(2)留学は、動機付けへとつながる「想像上のコミュニティ」の形成に貢献した、(3)8ヶ月以上留学した学生のみが自律的学習力を持つようになった、などがわかった。
Sasaki, M. (2006, April) (基調講演). The 150 Year history of English language assessment at schools in Japan. 2006 International Conference on English Instruction and Assessment, National Chung Cheng University, Taiwan.
要旨: 本研究は、日本の学校での英語教育における評価の歴史を概観したものである。日本の学校での正式な英語教育は、1860年の蕃書調所で始まった。本研究では、この年以来現在に至る約150年の文献を調査し、政府が設定した英語教育の目的に基づいて、(1)1860年~1945年(エリートのための英語教育)、(2)1945年~1970年(英語教育の実質義務教育化)、(3)1970年~1980年(コミュニケーションのための英語教育)、(4)1990年~現在(教育改革の中の英語教育)の4期に分けた。さらに、それぞれの時期の英語教育における評価に影響を与えた要因を、海外からの政治・経済的観点、国内の政治・経済的観点、文化的観点、人口動態的観点と学術的観点から詳しく論じた。それぞれの時期に英語教育の評価法に影響を与えた要因と影響力は様々であり、政策実施者の意図通りに運ばなかったこともしばしばであった。そのような歴史を踏まえて、教育評価における歴史研究の意義と、将来の新政策導入の際の留意点についても論じている。(基調講演)
Sasaki, M. (2005, July). A comparison of production questionnaires and role plays assessing L2 pragmatic competence. Language Testing Research Colloquium, Ottawa.
Sasaki, M. (2004a, March). Autoehnography of L1 and L2 literacies. The annual convention of Teachers of English to Speakers of Other Languages, Long Beach, California.
Sasaki, M. (2004b, May). Effects of study-abroad experiences on EFL writers: An exploratory multiple-data analysis. The annual conference of American Association of Applied Linguistics, Portland, Oregon.
Sasaki, M. (2004c, August). (招待講演). Outesunografi no kokoromi: Daini gengo de kaku to iukoto [An attempt of "aotoethnography: Writing in a second language]." E-Step Seminar, Hiroshima.
Sasaki, M. (2002a, October). (招待講演). Hypothesis generation and hypothesis testing: Two complementary studies of EFL writing processes. The Third Symposium on Second Language Writing, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
Sasaki, M. (2002b, April). (Colloquium Presenter) A multiple-data analysis of the three-year development of EFL students' writing processes. The annual conference of American Association of Applied Linguistics, Salt Lake City, Utah.
Sasaki, M. (2001). The development of EFL students' writing processes over a three year period. The Fourth Pacific Second Language Research Forum, University of Hawai'i at Manoa.
Sasaki, M. (2000, September). Toward an empirical model of EFL students' writing processes. The Second Symposium on Second Language Writing, Purdue University, West Lafayette, Indiana.
Sasaki, M. (1998, March). (基調講演). Toward an empirical model of L2 writing processes. The Third Pacific Second Language Research Forum, Aoyama Gakuin University, Tokyo.
要旨: 本研究は、第2言語学習者の文章産出モデルを試行的に構築することを目的としている。具体的には、「熟練した書き手」と「未熟な書き手」が意見文を書くプロセスのプロトコルデータを詳細に調査・比較した。その結果、能カモデルを包含し、プランニングやモニター行動を組み込んだ新しいタイプのプロセスモデルが完成した。
Sasaki, M. (1995). Assessing Japanese students' pragmatic competence in English as a foreign language: A comparison of production questionnaires and role plays. The annual conference of American Association of Applied Linguistics, Long Beach, California.
(1995年以前の研究発表はここには記載していません。)
その他
佐々木 みゆき(2016年3月)
英語教育時評:ソシオリテラシーを意識したジャンル教授法とは?
『英語教育』 p. 39
佐々木 みゆき(2015年11月)
英語教育時評:1ページの第二言語習得研究の歴史
『英語教育』 p. 37
佐々木 みゆき(2015年7月)
英語教育時評:Zoltán Dörnyei先生久々の日本講演!!
『英語教育』 p. 41
佐々木 みゆき(2015年3月)
英語教育時評:高校英語教育での「表現活動」が目指すもの
『英語教育』 p. 41
佐々木 みゆき(2014年7月)
英語教育時評:教職課程に必要な科目
『英語教育』 p. 43
佐々木 みゆき(2014年11月)
英語教育時評:Paul Kei Matsuda氏のこと
『英語教育』 p. 41
佐々木 みゆき(2012年4月)
書評:白井恭弘著『英語教師のための第二言語習得論入門』
『英語教育』 p. 93
要旨: この書評では、2012年1月発売の、白井恭弘著「英語教師のための第二言語習得論入門」を雑誌「英語教育」のBook Reviewsというページで評した。対象となった本は、前半は、第二言語習得論の最新の知見をやさしく語りかけるような文体で書いてあり、後半は、その理論を、小学校、中学校、高校、大学・社会人の各レベルでどのように具体的に生かせるかが書いてある。全体としては、題名通り、英語教師にとって有益な本であり、「新学期のプレゼントに最適の一冊」として読者に推薦している。
佐々木 みゆき(2011年1月)
日本の研究の未来を支える英語力:「辺境」からも元気に発信しよう!
単著『英語教育』 pp. 21-23
要旨: 「日本を支える英語教育とは」という新年特集号の記事の一つとして、「将来日本人が研究者としてグローバルに活躍するためには、どのような英語力が必要か」をテーマとして書かれたものである。応用言語学の中心が欧米にあるため、距離的にも学問的にも「辺境」の研究者として生きてきた自分自身の経験をもとに、「研究力」「実践スピーキング力」「実践ライティング力」「実践人間力」に分けて、それぞれに必要な技能や知識を具体的に論じている。「辺境」の研究者に有利な題材もあり、その強みを生かして主流派の学問地図を変えることも可能である。その意味では「辺境」の研究者も悪くないが、一方「主流」の研究者も日本人の中から多く出てほしいという希望も述べて、記事を結んだ。
佐々木 みゆき(2011年10月)
こんなときには、こんな<ことば>を贈りたい:ポジティブになりたい時
『英語教育』 pp. 22-23
要旨: 本記事は、『生徒・教師を支える「ことばの力」:名言・格言大特集』というテーマの英語教員向け雑誌「英語教育」増刊号の様々な記事のうち、「ポジティブになりたいとき」という題で書かれたものである。著者が英語教師として生きて来た中で、その後の教師としての姿勢に大きく影響を与えた言葉や、書いてもらってうれしかった言葉、元気が出る言葉、英語を教える上で常に心に留めておきたい言葉などを、その言葉に出会った時のエピソードとともに紹介している。
佐々木 みゆき(2010年1月)
もしも中学生の自分に会えたなら
『英語教育』 pp. 26-27
要旨: 本稿は、タイムマシンに乗り「もし中学生だった自分に会えたら」どんなアドバイスをするかを記したエッセイである。本稿執筆時までの著者の経験を踏まえて、もし、将来応用言語学者になるとわかっていて、英語学習をやり直せるなら、「やっておいてよかったこと」と、「やっておけばよかったこと」を記している。全体としては、アカデミックな分野に限定しての「日本での英語教育目標論」となっている。
佐々木 みゆき(2009年2月)
アウトプットとしてのライティング活動:書く力とやる気の研究最前線
『英語教育』 pp. 37-39
要旨: 本稿は、「インプットからアウトプットへ:SLA研究と現場を結ぶ」という特集を構成する記事である。まず、過去20年間の「第2言語ライティングの研究」の変遷を「What → How → Why」の3つのキーワードで概観した。具体的には、従来から行われていたライティング能力やライティングプロセスを説明しようとする実証的研究が、近年、動機付け研究に関わる社会文化的アプローチの研究に影響されつつある実態を詳述した。最後に、そのような変遷と現在の研究成果が、教育現場にどのような示唆をもたらすのかも考察した。
佐々木 みゆき(2008年4月)
Multi-competenceでいこう!:元気が出る実践英語のススメ(1):
「使える英語力」って?
『英語教育』 pp. 68-69
要旨: 本稿は、「Multi-competenceでいこう!」という6回連続の連載の第1回の記事である。具体的には、近年応用言語学の世界で注目されているmulti-competence(第2言語能力は、(どんなに低くても)第一言語と相互に作用して、より高い能力を作る付加価値である)の考えを紹介し、従来の日本の英語教育を支配してきた「ネイティブ信仰」とは違った角度から残り5回の連載記事を書くという意図を説明している。
佐々木 みゆき(2008年5月)
Multi-competenceでいこう!:元気が出る実践英語のススメ(2)
実践英語:ライティング編
『英語教育』 pp. 44-45
要旨: 本稿は、「Multi-competenceでいこう!」という6回連続の連載の第2回の記事である。具体的には、「国際雑誌に英語の論文を載せる」という「第2言語としての英語ライティング」行為にはどのようなプロセスが関わっているのかを個人的経験を交えて書き、それがうまくいくために「学校英語」の何が役に立ち、何が役に立たなかったかを考察することで、学習者のmulti-competence(第2言語を学ぶことで身に付く付加価値的能力)を生かす道を提案している。
佐々木 みゆき(2008年6月)
Multi-competenceでいこう!:元気が出る実践英語のススメ(3)
実践英語:リスニング編
『英語教育』 pp. 44-45
要旨: 本稿は、「Multi-competenceでいこう!」という6回連続の連載の第3回の記事である。具体的には、「英語のセミナーに参加する」という「第2言語としての英語リスニング」行為にはどのようなプロセスが関わっているのかを個人的経験を交えて書き、それがうまくいくために「学校英語」の何が役に立ち、何が役に立たなかったかを考察することで、学習者のmulti-competence(第2言語を学ぶことで身に付く付加価値的能力)を生かす道を提案している。
佐々木 みゆき(2008年7月)
Multi-competenceでいこう!:元気が出る実践英語のススメ(4)
実践英語:スピーキング編
『英語教育』 pp. 42-43
要旨: 本稿は、「Multi-competenceでいこう!」という6回連続の連載の第4回の記事である。具体的には、「国際学会で基調講演をする」という「第2言語としての英語スピーキング」行為にはどのようなプロセスが関わっているのかを個人的経験を交えて書き、それがうまくいくために「学校英語」の何が役に立ち、何が役に立たなかったかを考察することで、学習者のmulti-competence(第2言語を学ぶことで身に付く付加価値的能力)を生かす道を提案している。
佐々木 みゆき(2008年8月)
Multi-competenceでいこう!:元気が出る実践英語のススメ(5)
実践英語:リーディング編
『英語教育』 pp. 48-49
要旨: 本稿は、「Multi-competenceでいこう!」という6回連続の連載の第5回の記事である。具体的には、「英語で学会発表をするために文献を読む」という「第2言語としての英語リーディング」行為にはどのようなプロセスが関わっているのかを個人的経験を交えて書き、それがうまくいくために「学校英語」の何が役に立ち、何が役に立たなかったかを考察することで、学習者のmulti-competence(第2言語を学ぶことで身に付く付加価値的能力)を生かす道を提案している。
佐々木 みゆき(2008年9月)
Multi-competenceでいこう!:元気が出る実践英語のススメ(6)
実践英語:テスト編
『英語教育』 pp. 48-49
要旨: 本稿は、「Multi-competenceでいこう!」という6回連続の連載の最終回の記事である。具体的には、「TOEFLiBTとTOEICを受験する」という「第2言語のアカデミックなテストを受ける」という行為にはどのようなプロセスが関わっているのかを個人的経験を交えて書き、それがうまくいくために「学校英語」の何が役に立ち、何が役に立たなかったかを考察することで、学習者のmulti-competence(第2言語を学ぶことで身に付く付加価値的能力)を生かす道を提案している。
佐々木 みゆき(2007年8月)
先生だって元気になりたい!
『英語教育』 pp. 10-11
要旨: 本稿は、「夏休みブックガイド:私の選んだベスト3」という特集の記事である。具体的には、主に中学・高校の英語の先生向けに、(1)教えることに関わる1冊、(2)学ぶならこの1冊、(3)楽しめる1冊の3つのテーマで、夏休みに読むのに最適の本について、背景を説明し、書評したものである。
研究助成及び研究活動における受賞歴
科学研究費補助金
2020年4月〜2023年3月
基盤研究(B):第3言語圏留学がもたらすもの:多言語他文化社会で「生きる力」への長期的影響:課題番号20H01286
特別研究奨励金
2019年5月
令和元年度 名古屋市立大学特別研究奨励費
特別研究奨励金
2019年5月
令和元年度 名古屋市立大学特別研究奨励費
受賞
2018年10月
平成30年度 名古屋市立大学人間文化研究科 高インパクト論文賞
科学研究費補助金
2017年4月〜2020年3月
基盤研究(C):日本人学習者のウェブ上英語ライティング行動における「読み手意識」の長期的発達:課題番号17K02977
安倍フェローシップ
2016年8月〜2018年3月
Effects of web-based communication tasks on the development of a sense of audience in learners of Japanese as an L2
科学研究費補助金
2012年4月〜2016年3月
基盤研究(C):第二言語ライティング行動の長期的発達:ダイナミックシステム理論からのアプローチ:課題番号24520666
2010年5月
Language Learning Small Grants Research Program (granted for the Roundtable presenters organized by Professor Ilona Leki of the University of Tennessee, “Cross-Pollinations in L2 Writing Research across Continents” held at the Symposium on Second Language Writing at the University of Murcia, May 2010)
科学研究費補助金
2008年4月〜2012年3月
基盤研究(C):社会・認知的視点から見た外国語としての英語ライティング力と動機づけの長期的発達:課題番号20520533
科学研究費補助金
2006年4月〜2008年3月
基盤研究(C):第2言語としての英語産出モデルの構築:長期的発達と社会文化的影響の視点から:課題番号18520461
科学研究費補助金
2002年4月〜2006年3月
基盤研究(C):長期的発達の視点からの英語文章産出モデルの構築:課題番号14580311
公益財団法人 市原国際奨学財団研究助成金
2002年4月〜2003年3月
長期的発達の視点からの英語文章産出モデルの構築
科学研究費補助金
1997年4月〜2001年3月
基盤研究(C):英語文章産出モデルの構築:より効果的な営為作文指導のために:課題番号09680289
科学研究費補助金
1996年4月〜1997年3月
奨励研究(A):英語の語用論的能力を測る2つのテスト方法の比較と妥当性の検討:課題番号08780203
科学研究費補助金
1993年4月〜1994年3月
奨励研究(A):外国語としての英語の語用論的能力を測る熟達度テストの開発:課題番号05858039
科学研究費補助金
1992年4月〜1993年3月
奨励研究(A):発話行為能力を測る熟達度テストの開発に関する基礎研究:課題番号04858084
受賞
1990年
カリフォルニア大学ロサンゼルス校応用言語学部 Nida賞(1990年度博士課程ベスト論文賞)
留学奨学金
1984年〜1985年
ロータリー財団留学奨学金
留学奨学金
1980年〜1981年
日本政府国費給付留学奨学金
指導論文
博士論文
- - (2015). Peer review use in the EFL writing classroom.
- - (2014). Emergent leaders and small groups in the EFL classroom.
- - (2012). Peer review use in the EFL writing classroom.
- - (2011). A study of EFL argumentative strategies: Factors that affect the choice of organizational pattern.
- - (2006). Setting multiple standards on performance assessment for foreign language proficiency certification.
- - (2003). Learnability of explicit and implicit metaknowledge in second language writing.
- - (2001). Relationships among strategy use, foreign language aptitude, and second language proficiency: A structural equation modeling approach.
修士論文
- - (2018). Effects of collaborative teaching on junior high school students' explicit understanding of L2 grammatical items: A mixed method approach.
- - (2010). An Investigation of the Alternation of Adjective Comparative Forms in Indian and British English
- - (2010). Factors influencing students’ perceptions of feedback on writing in Japanese as an L2: An exploratory study.
- - (2008). The effects of a short-stay abroad on Japanese EFL students’ L2 learning motivation and other affective factors.
- - (2006). A study of gratitude expressions in the English of Japanese native speakers "Thank you" and "Sorry."
- - (2004). Developing a study abroad program and evaluation system.
- - (2003). Recollections and Hopes: The life-long-English-as-a-second-language learning process of elderly Japanese, with special attention to motivation and historical/political/social factors.
- - (2002). A study of Japanese EFL students' strategies for listening comprehension tests and the development of these strategies: A comparison of high and low proficiency students.
- - (2001). The second language acquisition of Japan Sign Language: An introspective approach.